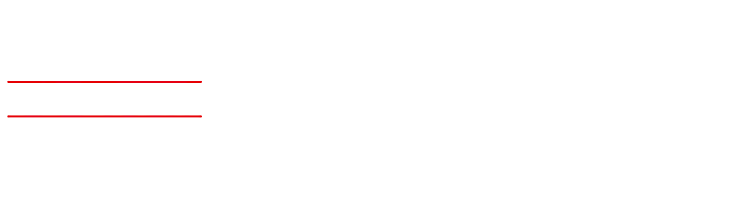降伏点とは?意味・求め方・材料強度との関係を徹底解説

降伏点とは?材料特性と設計への影響を徹底解説|金属加工・機械設計で重要な基準
降伏点とは、材料に外力を加えた際、弾性変形から塑性変形に移行する境界を示す応力値です。設計や加工では、降伏点を把握することで部品の強度、安全性、耐久性を正確に評価できます。本記事では降伏点の定義、測定方法、材料別の特徴、応用例、設計や加工への影響まで幅広く解説します。
降伏点の基礎知識
材料に力を加えると、最初は弾性変形が生じます。この弾性変形は、応力を取り除けば材料は元の形状に戻ります。しかし、応力がある値を超えると、材料は永久変形する「塑性変形」を始めます。この弾性変形と塑性変形の境界を降伏点と呼びます。
応力ひずみ線図での降伏点の位置
引張試験の結果を示す応力ひずみ線図では、降伏点は弾性直線を超えた位置に現れます。鋼材の場合、上降伏点と下降伏点が存在する場合があります。設計では一般的に下降伏点を使用して材料の許容応力を決定します。

降伏点の測定方法
降伏点は材料の特性により直接観測できる場合と、間接的に求める場合があります。最も一般的な方法は引張試験です。応力とひずみを測定し、塑性変形が始まる点を降伏点として定義します。
0.2%オフセット法
アルミニウムや銅など、明確な降伏点が現れない材料では「0.2%オフセット法」が用いられます。弾性線に平行な直線を、0.2%のひずみ点から引き、その交点を降伏点として定義します。これは設計上の実用的な降伏点として扱われます。
引張試験による測定
鋼材や炭素鋼では、JIS規格やASTM規格に従い、引張試験で荷重と伸びを測定します。応力ひずみ曲線を描き、下降伏点を読み取ることで設計用降伏点を決定します。
材料別の降伏点と特性
降伏点は材質によって大きく異なります。強度や加工性、安全率に直接影響するため、材料ごとの降伏点を理解することは非常に重要です。
| 材質 | 降伏点の目安 | 特徴 | 用途例 |
|---|---|---|---|
| SS400(一般構造用鋼) | 約245 MPa | 加工性と強度のバランスに優れる | 建築構造物、橋梁、機械部品 |
| S45C(炭素鋼) | 約355 MPa | 熱処理により強度向上可能 | 軸受、ギア、機械シャフト |
| ステンレス鋼(SUS304) | 約215 MPa | 耐食性に優れるが降伏点は中程度 | 厨房機器、化学装置、医療機器 |
| アルミニウム合金(A5052) | 約130 MPa | 軽量で加工性良好、明確な降伏点は少ない | 航空機部品、自動車部品、容器 |
| 銅 | 約70 MPa | 高い導電性を持つが強度は低い | 電気配線、熱交換器、装飾品 |
| チタン合金(Ti-6Al-4V) | 約830 MPa | 高強度かつ耐食性に優れる | 航空機部品、医療用インプラント |
降伏点と設計・安全率
降伏点は、構造物や機械部品の安全設計で不可欠です。使用する材料の降伏点を基準に許容応力を設定することで、過度の変形や破壊を防ぎます。
安全率の設定例
SS400鋼で降伏点が245 MPaの場合、安全率を1.5とすると、許容応力は約163 MPaになります。設計段階で許容応力を考慮することで、部品の寿命や安全性を確保します。
加工と降伏点の関係
塑性加工(曲げ、押出し、圧延、鍛造など)では降伏点を超える応力が必要です。降伏点を理解していないと、加工中に材料破損や不具合が生じる可能性があります。
熱処理による変化
鋼材は熱処理によって降伏点が大きく変化します。焼き入れや焼き戻しを行うことで降伏点と引張強度を高めることが可能です。一方、アルミニウム合金では時効硬化によって耐力が向上する場合があります。
降伏点と破断強度・弾性限界との違い
降伏点は材料が永久変形を始める応力であり、破断強度は材料が破壊する最大応力です。また、弾性限界は完全に弾性変形する範囲の限界点を示します。設計では降伏点を基準に安全設計を行い、破断強度は材料の限界値として参考にします。
よくある質問
Q. 降伏点とはどのような意味を持つのでしょうか?
Q. 降伏点はどのように測定されますか?
Q. 降伏点は設計や安全率にどのような影響を与えますか?
ご質問や加工相談はこちらから!
お気軽にお問い合わせください。
旋盤、フライス、切削加工、試作、短納期に強い大阪府守口市のフィリールへ。具体的な活用事例やご相談は以下からお問い合わせください。