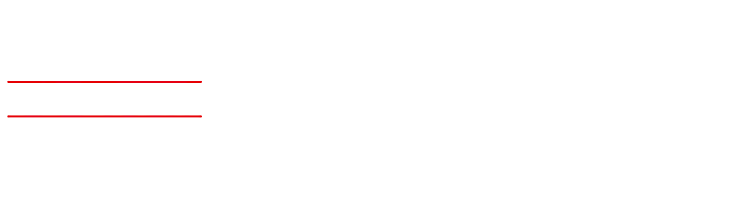調質材とは?記号の意味・JIS規格・用途まで徹底解説|指定で失敗しない完全ガイド

調質材とは?記号の意味・JIS規格・用途まで徹底解説|指定で失敗しない完全ガイド
製造や設計の現場で「調質材(ちょうしつざい)」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。調質材とは、焼入れと焼戻しを施して、硬さと靱性のバランスを取った鋼材のことを指します。しかし、同じ「H」や「丸H(Ⓗ)」の記号でも、JIS規格やメーカーによって意味が微妙に異なる場合があります。本記事では、調質材とは何か、その記号の意味、JIS規格における扱い、そして実務での指定・選定ポイントを徹底解説します。
調質材とは?焼入れ・焼戻し処理の目的と原理
調質材は、鋼材を焼入れと焼戻しという2段階の熱処理を施すことで、強度と靱性を両立させた状態の材料をいいます。単に硬くするだけの焼入れ材では割れやすく、柔らかすぎる焼なまし材では摩耗しやすいという欠点があります。その中間を狙って、「強いのに粘りがある」状態に仕上げたのが調質材です。
調質処理の基本工程
| 工程 | 温度範囲 | 目的 | 冷却方法 |
|---|---|---|---|
| 焼入れ | 800〜870℃ | マルテンサイト組織の生成 | 油冷・水冷・ガス冷 |
| 焼戻し | 500〜650℃ | 靱性回復・内部応力除去 | 空冷 |
この処理を事前に行った鋼材は「調質材」として流通し、加工後の熱処理が不要になるため、設計精度や寸法安定性が向上します。
調質記号の種類と意味|H・丸H・N・Aの違い
鋼材の調質状態は、記号で明示されます。一般的には以下のように区分されます。
| 記号 | 意味 | 熱処理状態 | 代表的用途 |
|---|---|---|---|
| H / Ⓗ(丸H) | 調質材 | 焼入れ+焼戻し済 | 歯車・軸・ボルト・機械構造部品 |
| N | 焼ならし材 | 焼入れ前の応力除去処理 | 一般構造部材 |
| A | 焼なまし材 | 軟化処理済み | 切削加工用素材 |
たとえば、「S45C-H」や「S45CⒽ」と表記されている場合、これはS45C鋼を調質処理した状態を意味します。ただし、SCM435Hのように“H”が単なる鋼種名に含まれているケースもあるため、実際に熱処理済かは仕様書の確認が必要です。
JIS規格における調質材の位置づけ
調質材は多くのJIS規格で明示されています。主なものを以下に示します。
| JIS規格番号 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| JIS G4051 | 炭素鋼 | S45Cなど機械構造用炭素鋼 |
| JIS G4105 | クロムモリブデン鋼 | SCM系鋼材(SCM435など) |
| JIS G4053 | ニッケルクロムモリブデン鋼 | SNCM系鋼材 |
これらの規格では、引張強さ・硬さ・伸びなどの機械的性質が範囲で定義されており、調質処理条件が明文化されています。詳細は日本鉄鋼連盟(JIS)で確認できます。
代表鋼種の機械的性質例
| 鋼種 | 引張強さ (MPa) | 硬さ (HB) | 伸び (%) | 衝撃値 (J/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| S45C-H | 600〜800 | 180〜240 | 15〜25 | ≥30 |
| SCM435-H | 900〜1100 | 270〜330 | 10〜20 | ≥35 |
| SNCM439-H | 950〜1200 | 300〜370 | 8〜18 | ≥40 |
これらの数値は目安であり、メーカーによって異なりますが、調質処理により高強度と粘り強さを両立できることが分かります。
調質材の用途と実用例
調質材は、以下のような部品に幅広く使用されています。
- 自動車部品(クランクシャフト、カムシャフト、ギア)
- 産業機械の軸類、ピン類、ロッド類
- 建設機械・ロボットアームのリンク構造部
- ねじ製品・ボルト(高強度部品)
たとえば、S45C調質材は高い加工性とバランスの良い機械的特性を持つため、汎用機械部品に多用されます。一方で、SCM435やSNCM439などは高温下や衝撃負荷を受ける環境に適しています。
具体的な熱処理プロセスの管理方法や温度履歴については、「焼入れ・焼戻し処理の工程と温度管理に関して解説」で詳しく説明しています。
他材質との比較|炭素鋼・合金鋼・ステンレスの調質特性
| 材質区分 | 代表例 | 調質の可否 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 炭素鋼 | S45C、S50C | 可 | 加工性良好・中強度 |
| 合金鋼 | SCM435、SNCM439 | 可 | 高強度・靱性・疲労特性優秀 |
| ステンレス鋼 | SUS420J2 | 可(焼戻し可) | 耐食性と強度両立 |
特にSCM435やSNCM439は、クロムやモリブデンの添加により焼入れ性が向上し、深部まで均一な調質が可能です。このため、厚肉シャフトなどにも適しています。
調質材を指定するときの注意点
設計図や発注書で調質材を指定する際には、以下の点を明確にしておく必要があります。
- 鋼種(例:S45C、SCM435)
- 記号(H、Ⓗ、Nなど)
- 規格番号(例:JIS G4051)
- 熱処理条件(目標硬さ・焼戻し温度)
- 試験方法・保証範囲
これを曖昧にすると、「H付き鋼材なのに未調質材だった」「熱処理後の硬さが想定より低い」といったトラブルが起きます。