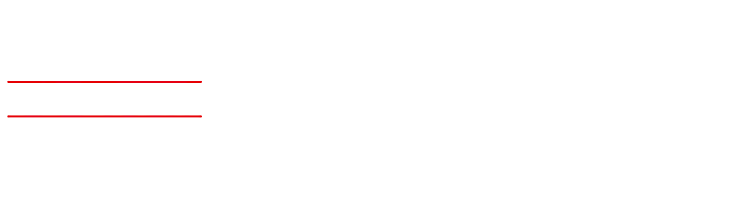許容応力とは?初心者にもわかりやすく解説|意味・計算方法・材質ごとの違い
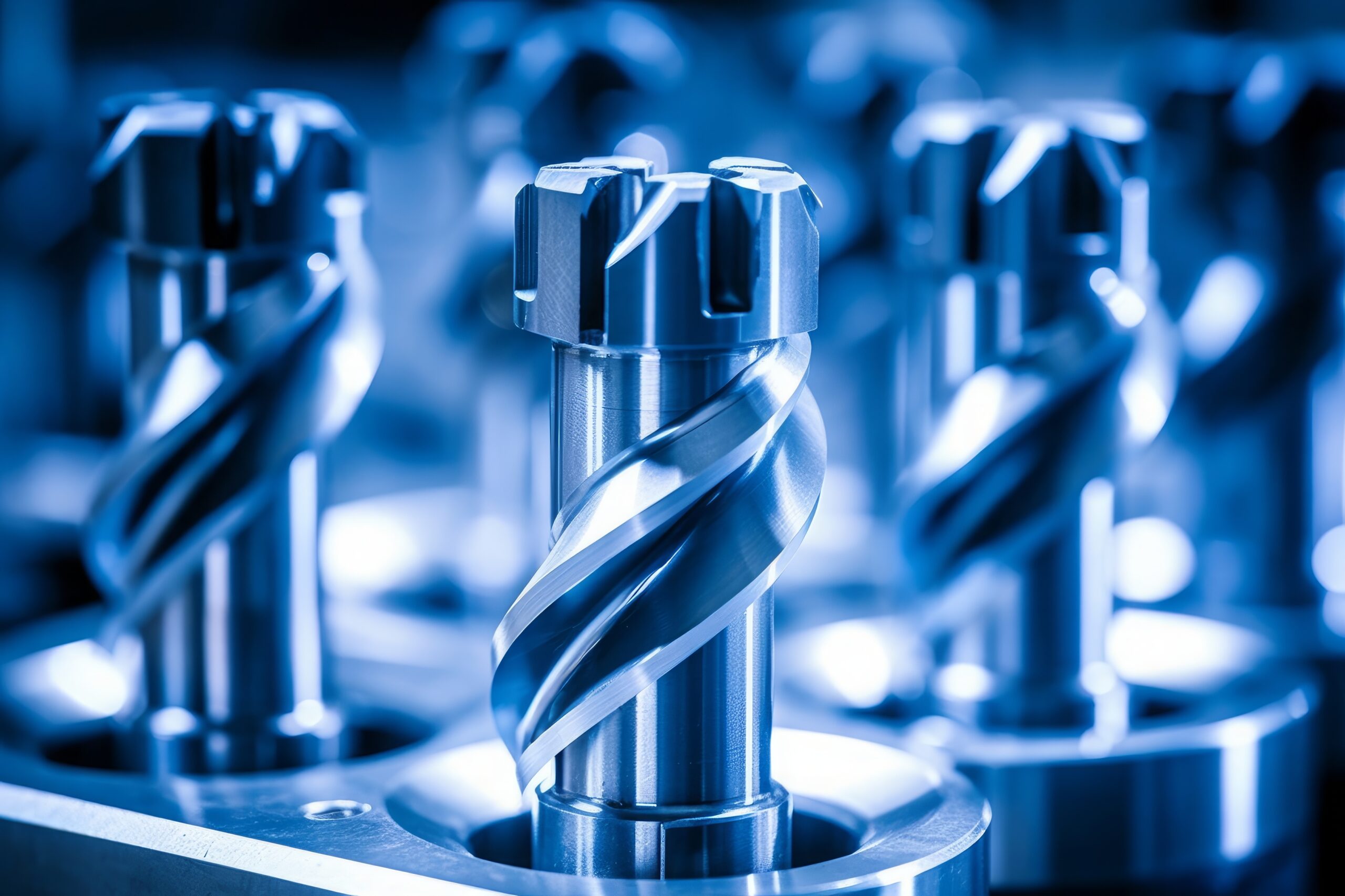
許容応力とは?初心者にもわかりやすく解説|意味・計算方法・材質ごとの違い
許容応力とは、設計や製造において「その材料が安全に使える応力の上限」を指す重要な指標です。引張強度や降伏点のような材料の性質をもとに算出され、設計の安全率を確保するために活用されます。本記事では、許容応力の基本的な意味から、算出方法、材質ごとの違い、設計上の考え方までを詳しく解説します。
1. 許容応力とは何か
許容応力とは、構造物や部品が安全に使用できる最大の応力を示した値です。設計者はこの値を基準に、部材の寸法や形状を決定します。もし許容応力を超える応力が加わると、変形や破壊のリスクが高まります。したがって、設計や評価における基準値として非常に重要です。
1-1. 応力の基本概念
応力(σ)は、材料に外力が加わったときの「力の強さ」を断面積あたりで表した値です。単位はMPa(メガパスカル)が使われます。例えば、引張応力や圧縮応力、せん断応力などがあり、許容応力はこれらを超えない範囲で設計されます。
1-2. 降伏点や引張強度との関係
許容応力は、材料の降伏点や引張強度をもとに算出されます。降伏点とは永久変形が始まる応力で、引張強度は破壊に至る最大応力です。許容応力はこれらの値を直接使うのではなく、安全率をかけて低めに設定します。
2. 許容応力の算出方法
許容応力は次のような計算式で求められることが多いです。
許容応力 = 材料の基準強度 ÷ 安全率
基準強度には、降伏点(σy)や引張強度(σu)を用います。安全率(n)は用途や信頼性の要求に応じて決められ、一般的には1.5〜3程度が採用されます。
2-1. 安全率の考え方
安全率は、設計における「余裕」を数値化したものです。例えば、降伏点が300MPaの鋼材に安全率2を設定すると、許容応力は150MPaになります。これにより、予期せぬ荷重や加工誤差があっても安全が確保されます。
2-2. 計算例
例えば、S45C鋼(機械構造用炭素鋼)の引張強度を600MPa、安全率を2とした場合、
許容応力 = 600 ÷ 2 = 300 MPa
となります。このようにして設計値を導きます。
3. 材質ごとの許容応力の目安
材質によって許容応力は大きく異なります。以下に代表的な素材の例を示します。
| 材料 | 基準強度 | 安全率 | 許容応力の目安 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| SS400鋼 | 400 MPa | 1.5~2.0 | 200~267 MPa | 建築構造材 |
| S45C鋼 | 600 MPa | 1.5~2.0 | 300~400 MPa | 機械部品、シャフト |
| SUS304ステンレス | 520 MPa | 1.5~2.0 | 260~346 MPa | 配管、食品機械 |
| A6061アルミ合金 | 310 MPa | 1.5~2.0 | 155~206 MPa | 航空機部品 |
| POM樹脂 | 65 MPa | 2.0~3.0 | 20~30 MPa | 歯車、摺動部品 |
| MCナイロン | 80 MPa | 2.0~3.0 | 27~40 MPa | スプロケット、ローラー |
3-1. 金属材料
金属は基準強度が高いため、許容応力も比較的大きく取れます。鋼材やステンレスは構造部材に広く使われています。特に金属材料の特性を理解することが設計には不可欠です。
3-2. 樹脂材料
樹脂は金属に比べて強度が低いため、許容応力も低くなります。ただし、軽量性や加工性に優れるため、設計に応じて適切に選定されます。
3-3. 複合材料
CFRPのような複合材料は引張強度が高く、許容応力も大きく設定できます。軽量化と高強度を両立できるため、航空宇宙やモータースポーツに不可欠です。
4. 許容応力と設計の関係
許容応力は設計に直結する値であり、過大評価や過小評価は製品の安全性に直結します。設計では応力解析を行い、許容応力を超えないことを確認することが不可欠です。
4-1. 許容応力設計法
許容応力設計法は、材料の強度と安全率を基準に設計する方法です。これは古典的で広く使われていますが、近年では限界状態設計法が主流になりつつあります。
4-2. 熱処理や加工の影響
同じ素材でも熱処理や加工方法によって基準強度が変化するため、許容応力も変わります。焼入れ鋼や析出硬化型アルミなどは処理次第で性能が大きく向上します。
よくある質問
Q. 許容応力とは何ですか?
Q. 許容応力はどのように計算されますか?
Q. 材質によって許容応力はどのように変わりますか?
Q. 許容応力と安全率の関係は?
5. まとめ
許容応力とは、材料が安全に使用できる応力の上限を意味します。引張強度や降伏点をもとに安全率を考慮して算出され、設計において重要な役割を果たします。材質や用途に応じた正しい設定が不可欠です。
ご質問や加工相談はこちらから!
お気軽にお問い合わせください。
旋盤、フライス、切削加工、試作、短納期に強い大阪府守口市のフィリールへ。具体的な活用事例やご相談は以下からお問い合わせください。